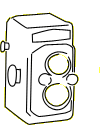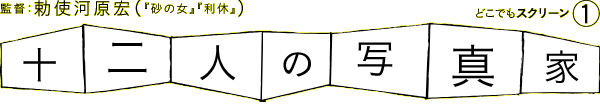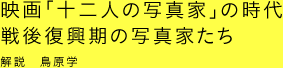映画「十二人の写真家」は、一九五五(昭和三〇)年に写真雑誌『フォトアート』(研光社・一九四九年創刊〜一九七七年休刊)の創刊六周年を記念し、読者に向けて制作された啓蒙映画である。
内容は文字通り、一線で活躍する十二人の写真家──木村伊兵衛、三木淳、林忠彦、早田雄二、渡辺義雄、稲村隆正、大竹省二、真継不二夫、秋山庄太郎、田村茂、濱谷浩、土門拳(以上、順不同)の撮影のもようを記録したものである。映画の企画は亀倉雄策、監督は勅使河原宏である。
映画の公開は同年五月一八日。東京銀座にある山葉ホールで同誌主催の「講演と映画の夕」が開催され、そのメインプログラムとして上映された。同誌の八月号によると映画に対する読者の関心は非常に高く、午後六時の開演時にはすでに満席になったとある。なかには映画を見るため、二日間かけて上京した地方のファンもいたようだ。
この一九五五年、戦後のカメラブームは第一回目のピークにあったといえる。機械統計によれば、日本のカメラの生産台数が初めて百万台を突破するのがこの年なのだ。日本は戦後復興期を終えて高度成長のとば口にあり、大衆の生活にゆとりが生まれはじめ、写真ファンが急増していった時期である。
すでに写真雑誌は十誌以上が刊行され、映画の前年には『カメラ毎日』(毎日新聞社)や『サンケイカメラ』(産経新聞社)が創刊されている。ちなみに、『カメラ毎日』がその創刊記念に招聘したのがロバート・キャパで、キャパは訪問した日本各所で圧倒的な歓迎を受けている。
さらにその前年、アンリ・カルティエ=ブレッソンの写真集『決定的瞬間』が輸入され、同書のタイトルは一種の流行語になっていた。
このキャパもカルティエ=ブレッソンも、報道写真家集団「マグナム」の創立メンバーである。彼らのような世界的に活躍する報道写真家への関心は、戦後日本の民主化にともなって、非常に高まっていたのだ。
そして、翌一九五六年三月には、ニューヨーク近代美術館の写真部長エドワード・スタイケンの企画による史上最大規模の写真展「ザ・ファミリー・オブ・マン(われら人間みな家族)展」が日本を巡回する。人類の普遍的な営みにみるヒューマニズムという、壮大なテーマを提示したこの展覧会の総入場者数は百万人を超えることになる。
こうした写真への関心の高まりのなか、「十二人の写真家」は公開され写真ファンの大きな感心を惹いた。しかし、一方で日本の写真は戦後十年を迎えたこの時期に、大きな曲がり角に差し掛かっていたようにも思える。一九五五年とは彼ら十二人の写真家にとって、どのような年であったのだろう。
映画が制作される前年、つまり一九五四年、土門拳は第一期リアリズム写真の終了を宣言している。
一九五〇年以来、土門は写真雑誌『カメラ』の月例コンテストの審査を通じて、全国のアマチュア写真家たちに社会的リアリズムに目覚めよと呼びかけていた。戦後の混乱する社会をカメラでリアルに直視すること、そのうえで近代的写真芸術の確立ができると土門は熱っぽく語った。土門の呼びかけは非常な反響を巻き起こし、おそらく日本写真史上で唯一、“大衆運動”と呼びうる展開を見せた。
その区切りを自らでつけた土門は、翌一九五五年一月に日本橋高島屋で「第一回個展」を開催し、五月にはこれまでの成果となる写真集を発表する予定であった。写真集のタイトルは『江東のこどもたち』で、版元のこの『フォトアート』誌上にも出版予告が打たれている。
『江東のこどもたち』は、東京の下町を駆け回る子どもたちを追った写真であり、戦後の東京の断面を捉えたものであった。この映画のなかにある土門の撮影風景は、『江東のこどもたち』の撮影風景か、それを再現したものである。しかし、この映画の公開直前に土門は写真集を諦めた。土門は『江東のこどもたち』に代表される作品を「小市民的リアリズム」と呼んだが、その小市民的な感覚を自省したからだ。その背景には急速な社会状況の変化があった。
一九五二年の講和条約発行後、警職法の改正問題や内灘や砂川など米軍基地を巡る大衆闘争が起きており、写真家には小市民的な感覚ではなく社会的な問題をテーマとすることが求められていた。もちろん、社会的なリアリズムを叫んだ土門自身が、この時代の変化を誰よりも深刻に感じていたに違いない。
映画のなかで、雄弁だった土門が『江東のこどもたち』については具体的に一言も語っていない。そのことがかえって、当時の彼の胸中を物語っているようにさえ思える。
一方、土門と並ぶ巨匠であり、ともにリアリズム写真運動を牽引してきた木村伊兵衛は、この頃すでに土門拳の行き方とはっきりと距離をおき、自らの写真のあり方を掴み直そうとしていた。
一九五五年の木村は「木村伊兵衛外遊作品展」を開催している。前年に初めてヨーロッパへの取材に出かけ、その写真をまとめたものである。
この旅での大きな収穫は、パリでカルティエ=ブレッソンの自宅を訪れたことであった。映画でも述べているように、カルティエ=ブレッソンとの語らいは、木村にライカによるスナップ写真の美学を再発見させた。この後、木村はより自由な視点で、東京を中心に庶民の生活をスナップしていくのである。
戦後復興期の終わり、写真界を牽引してきた土門も木村も、大きな分岐点に立っていたのである。
「十二人の写真家」に登場する写真家たちは、その経歴から大きく三つのグループにわけられる。
ひとつのグループは、世代的には明治生まれになる。彼らは戦前すでに指導的な立場で活躍していた写真家たちで、さきの土門と木村に加えて渡辺義雄、真継不二夫、田村茂がそれにあたる。この世代の共通点のひとつは、戦中に国策に協力したことに対する反省を持っていたことである。リアリズム写真は、その反省が生んだ運動という一面がある。
たとえば戦前に始まる報道写真の先駆的な写真家であり、建築写真の第一人者であった渡辺は、戦後しばらく写真家としての本格的な活動をしばらく控え、携わっていた写真教育の現場からも身を引こうとしていた。また戦前はファッションの分野でも活躍していた田村は、敗戦後に共産党に入党して、階級闘争的な歴史観を再出発の起点におき、労働争議などを取材した。
一九五五年当時、渡辺も田村も再び第一線で活躍していた。この映画のなかで渡辺は、復興期の代表的な建築のひとつである神奈川県立音楽堂を撮影し、田村は正式な国交のまだなかった中国共産党の国際貿易代表団の来日を取材している。彼らの撮影シーンのなかからは、戦後におけるその生き方が見えてくる部分がある。
戦時体制が強化されるなか写真家としてスタートしたのが林忠彦、早田雄二、濱谷浩の三名。彼らは戦後いち早く一線に復帰した写真家でもあった。
なかでも林は一九四五年に上京すると、戦後の出版ブームで登場したあらゆる類の雑誌の仕事を引き受けた。そして一九四七年、写真雑誌で発表した戦後無頼派の作家太宰治のポートレイトが評判を呼び、翌年『小説新潮』誌の連載によって、新進写真家としての地位を確立した。映画のなか林は武者小路実篤を被写体に、もっとも得意とする文士の撮影シーンを見せている。
早田は一九四六年に復員すると、戦前から携わっていた映画雑誌『映画ファン』にカメラマンとして復帰した。当時、映画は娯楽の王様であり、早田は多忙を極めた。一九五五年当時の早田はおもにスタジオ撮影における、ライティングや撮影法の向上に余念がなかった。この映画ではそんな側面に光が当てられている。
濱谷は戦中に軍関係に協力することを拒否し、大戦中も新潟の村落に伝わる民俗行事を取材していた。一九五五年、濱谷は長く撮り続けた民俗の写真をまとめた写真集『雪国』の出版を翌年に控えていた。映画で捉えられているのは『雪国』に続く、日本海側に住む人々の太平洋岸に比べ格差のある実態をルポした『裏日本』の撮影の様子である。土門流のリアリズムとは違う、静かな視点で日本を見つめたこの二冊の写真集が、戦後世代の写真家に与えた影響は極めて大きい。
最後の三木淳、秋山庄太郎、稲村隆正、大竹省二の四名は、大正生まれという点では濱谷らと同じ世代ではある。
だが、一般大学を卒業して兵役につき、戦後に写真家として出発した点で大きく異なる。つまり三木は慶応、秋山と稲村は早稲田、そして大竹は東亜同文書院を卒業している。戦前の平時であれば、一般の大学生が卒業後に写真家になることなど極めて異例なことであった。いや一九五〇年代頃まで“写真家”という職業名さえ一般的ではなく、その社会的地位はかなり低かったといわれている。敗戦という出来事が、その流れを変えたのである。
そんな意味においても、彼らの登場は「アプレゲール(価値紊乱者)」という名で呼ばれた戦後世代にふさわしく、写真の世界に新たな風を吹き込んだ。
なかでも三木は、一九四九年に日本人で初めて、国際的なグラフ誌『ライフ』を発行するタイムライフ社に正式に入社、報道写真における戦後世代の旗手と目されていた。
しかし一九五四年に初めて渡米した頃から、『ライフ』の商業優先的な雰囲気に、三木は違和感を覚えるようになる。さらにこの一九五五年に朝鮮戦争が休戦すると、極東地域の報道価値が薄れたことも、自らの立場を考え直すきっかけになった。『ライフ』はやはりアメリカ人のメディアであり、日本人である自分はどうすべきかと三木は自問自答を繰り返すようになっている。
大竹、秋山、稲村らは、この頃すでに女性専門の写真家として知られるようになっていた。この映画のなかでも、彼らのシーンはもっとも華やかな感じがするのではないか。
一九五〇年代半ば以降、彼らの活躍の場は急速に拡大していった。週刊誌やファッション誌の創刊ラッシュのなかで、その表紙写真やグラビアページを担当して大衆的な人気を獲得し、それゆえタレントや実業といった面でも才能を発揮する者も現れる。
映画「十二人の写真家」が作られた一九五五年の日本は、戦後復興期から高度成長期への移行期、つまり二つの時代の谷間にあった。それゆえ、日本社会が写真家にもとめるものの質も、写真をとりまくメディアの状況も急速に変わりはじめていた。
これら十二人の写真家たちのその後を見ると、それぞれがそれぞれの思いを抱えながらも環境の変化に対応し、代表作というべき仕事を発表していくのである。この映画のなかには、現代に繋がる戦後写真の原形というものが現れているようにも思われる。
(とりはら まなぶ・写真研究家)